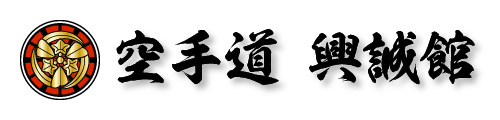格闘技の「型」は何故大事なのか?
空手をはじめ、テコンドー、拳法、古武術などには、一定の決まった動きを反復練習するものが多くあります。
ほんのわずかな動作数しかないため、型と呼ばれない動きから、50動作、100動作もある立派な型まで様々です。
*今回は「かた」を「型」と表記させていただきます。「形」と書く団体もあり、国際大会ではpattern(パターン)と訳されることも。
①型は流派によって様々です。
正しいとされる動きの違い、細かい部分の途中動作の違い、軌道や攻撃部位の違い、狙いとするものの違いなど、一般の方が見てもなかなか違いは分かりにくいかもしれません。型の名前をとっても、伝統派の空手にある「スーパーリンペイ」「セーパイ」など、語源や意味が明らかでない名前も多く、琉球語や中国語の古語に由来するとか、色々な国の言葉が混ざったなど、所説あるようです。人名を型の名前にしている団体もあれば、興誠館のように海の自然現象から命名する団体もあります。
②型は何故練習するのか?
多くの練習生が最初にぶつかる疑問かもしれません。「組手だけしていればいい」と思っていたら師匠から「型の練習もしなさい」と言われたり・・・・。
最も一般的な理由は「型は組手で使える大事な動作が詰め込まれており、反復練習を通して強くなれる」という理由でしょう。目の前に敵がいると想定して練習しなさい、とは流派を問わずどこでも教えられることでないでしょうか。
また、個人的に好きな理由としては「型は思いを表現できるように練習する」という理由です。型に人名や神名を付けた団体は特にその傾向があるようで、型には思いや感情をこめて演武することが求められます。もちろん思いや感情をこめるには、基本となる身体動作がしっかりできていなければ論外です。亡くなった方への思慕の気持ちや敬愛の気持ち、あるいは力強さや冷静さを表現したり、歌や踊りがそうであるように、型にもまたそうした「思い」を乗せることができます。
型の練習は、まず全体の動作を覚えること、一つ一つの技の意味や役目を理解すること、それらを一連の流れでスムーズに演武しきれること、最後に思いを乗せること。とにかく繰り返し繰り返し練習することで、誰でも必ず上達するのが型です。
空手をやる楽しみとして、型を覚えるのが好きという方も多くいらっしゃいます。そういう楽しみ方もまた、空手だと思います。
ぜひ、型を大切に練習しましょう!